こちらは、こだわりの玄米販売しているスズノブ【千葉店】のオンラインショップです
こちらの商品は、販売を終了致しました。 |
||
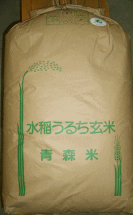 |
年産 | 2011年 |
| 産地 | 青森県 | |
| 地域 | 指定なし | |
| 品種 | つがるロマン | |
| 検査代理人 | 指定なし | |
| 栽培方法 | 慣行栽培 | |
| 等級 | 1等 | |
| コード | 2102011 | |
| 米袋の形態は変更になる場合があります | ||
| 玄米30kgで約200合 1日5合炊くと 約40日分 | 1合当たり約62円 |
| お茶碗1杯 約170g で計算すると30kgで 400杯 | 1杯当たり約31円 |
配送形態はリサイクルを兼ねて30㎏の紙袋にお米を入れて送ります。 |
| 作付け産地 | つがるロマンとは |
| 青森県 | つがるロマンは、1983年に青森県農業試験場にて「ふ系141号」と「あきたこまち」を掛け合わせて作られました。 「つがるおとめ」の代わりに、あおもり米のエースとして誕生し期待を背負っております。 津軽富士「岩木山」をのぞむ津軽中央地帯を中心に、津軽西北、さらに南部平野内陸地帯での気象・土壌条件の良好な適地で作付けされています。 炊き上がりは香りが良く、弾力性・食感が良くお酢との相性がいい為お寿司屋さんにも人気のある品種です。 つがるロマンのネーミングは、全国から応募のあった、8,861点の名前の中から選ばれ青森県の、そして日本のお米づくりの里である津軽を発祥の地として、全国有数の銘柄になるよう青森県の稲作生産者の願いを込めロマンあふれるネーミングです。 |
| 地域情報 | 主な行事 |
| 青森県は東北地方の北部に位置する本州最北端の県である 南に岩手県、秋田県が隣接し、津軽海峡を渡った北に北海道が位置する。 東に太平洋、西に日本海が面する。 世界遺産白神山地を有し、景勝地十和田湖をはじめ八甲田山、岩木山、下 北半島の仏ヵ浦などの自然環境が数多く残されている。 青森県の中央部には奥羽山脈が縦走し、西側の津軽地方と東側が南部地方(三八地方・上北地方・下北地方)ではそれぞれ異なる歴史や気候、文化、風土をもっています。 青森県は全国有数の農業産出県であり、食料自給率はカロリーベースで 118%であり。 主要な出荷品目はりんご、ナガイモ、にんにくが、全国一の生産量である。漁業においても全国有数の水揚高を誇る八戸港が あり、サバ、イカが国内一の水揚げがあり全国に出荷されている。 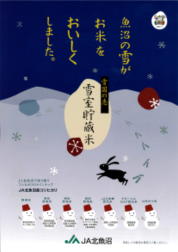 年間平均気温 約10.1度 年間平均降水量 約1289㎜ |
青森ねぶた祭
東北三大祭りの一つで、毎年8月2日~7日の日程で開催される青森ねぶた祭は、二十数台の大型ねぶたが出陣し、約3.1kmのコースを2日~6日は夜、最終日の7日は昼に運行されます。正装衣装を着ていれば、誰でも参加することが出来ます。昭和55年、国の「重要無形民俗文化財」に指定されました。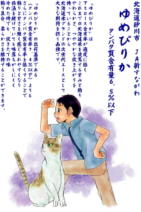 弘前ねぷたまつり
国の重要無形民俗文化財に指定されている弘前ねぷた。正史に表れるのは享保7年。藩日記に5代藩主信寿公がねぷたを見物したという記録が残されています。 また「津軽剛情っ張り大太鼓」は、負けず嫌いだったという3代藩主信義が作らせたのが始まりといわれています。 毎年8月1日~8月7日に開催されている弘前ねぷたまつりは、勇壮で幻想的な武者絵などが描かれた扇ねぷたや組ねぷたなどが運行されます。 八戸三社大祭
 280年余の歴史と伝統を誇る東北屈指の華やかな祭り。毎年7月31日から8月4日に開催され、江戸・京都方面から買い入れた人形を台の上に乗せ、かけ声も勇ましく練り歩いたのが事の起こり。時代と共に趣向と工夫を凝らし、各町内が華麗さを競って山車づくりをするようになりました。 |
| コメの放射性物質検査 |
| 青森県では、国の方針に基づき、平成23年産米の放射性物質検査を実施しました。 その結果、県内全市町村において放射性物質は検出されず、県産米(飼料用米を含む)の安全性が確認され、通常どおり出荷・販売ができるようになりました。 コメの放射性セシウムの暫定基準値は、1キロ当たり500ベクレル。基準値を超すセシウムが検出されれば市町村単位で出荷が制限されます。 基準値以下でも、200ベクレルを超す場合は、検査箇所を増やし再検査を致します。 検査結果がすべて国の暫定基準値以下となった時点で出荷・販売が可能になります。 検査結果は青森県のホームページでご覧になれます。 |
